外せない選手に決まった大迫勇也の有効な活用法。1トップ下の方が面白い?

写真:Shigeki SUGIYAMA
年齢を重ねると1年が早く感じられるとは、多くの読者も実感されていることだと思う。W杯とW杯の間隔も同様。今回のカタール大会は、筆者にとっては通算11回目の現地取材になるが、その4年間は感覚的に狭まるばかりだ。今回は通常より半年間分、長いはずなのにその実感は湧いてこない。あっという間に過ぎ去った4年半だった。
4年半前、日本がロストフでベルギーに大逆転負けした時、なによりドラマ仕立ての展開に酔いしれたものだ。敗戦を悔しがりながらも、次の4年半に対して、明るい希望を抱くことができた。
つまり筆者は日本サッカーの4年後を想像することに慣れている。これまでの人生において、W杯が終わった瞬間、4年後の日本をその現場で想像する機会が少なくとも過去に10回あった。8年前、12年前、16年前……も、同じ思いを巡らしている。
なので、何が無理で、何が達成可能かの見極めは付くつもりである。4年後はベスト4だとか、変に威勢のいい台詞は、口が裂けてもいう気になれない。2050年までにW杯優勝という目標を立てている日本サッカー協会にも、懐疑的にならざるを得ない。ロストフの現場で想像した4年後は、最大ベスト8。その可能性は20%となる。
そうした前提に立ったとき、なにより痛感したのが、大舞台で、目まぐるしい展開になっても、的確な選手交代ができる監督の必要性である。西野さんを見ていると日本人監督では正直、難しいと感じた。浮沈カギを握るのは代表監督。森保氏の代表監督就任にはそうした意味で、落胆せずにはいられなかった。森保監督は就任会見で目標は「ベスト8」と述べた。しかしその瞬間、筆者の期待は20%から10〜15%に萎むことになった。
一方、選手に対しては心配しなかった。いま以上の選手は次々に現れるだろうと楽観的でいた。
ロシアW杯。様々な幸運が日本のベスト16入りを後押ししたことは確かだった。しかし、日本がよいサッカーをしたこともまた確かで、過去6大会の中で、断トツによかった。なによりバランスが取れていた。選手を綺麗に並べたのは西野監督で、その点については拍手を送りたくなるが、その中心に位置したのが大迫勇也だった。
(残り 2189文字/全文: 3115文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


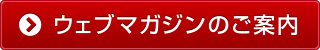
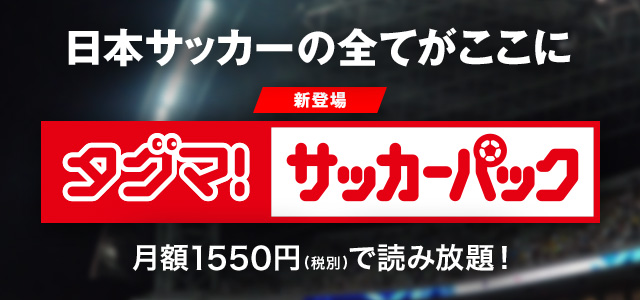





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ